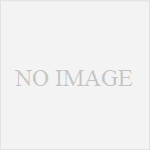
香水
この出だしで一気にストーリーのはじまりを予感させます。しかも、二人の関係性もわかるのですから、なんとも絶妙です。本当に素人が作ったのは思えない出だしです。 ♪別に君を求めてないけど 横にいると思い出す ♪君のドルチェ&ガッバーナの その香水のせいだよ このサビの部分でメロディーと歌詞が見事に合わされている
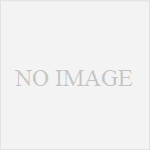
この出だしで一気にストーリーのはじまりを予感させます。しかも、二人の関係性もわかるのですから、なんとも絶妙です。本当に素人が作ったのは思えない出だしです。 ♪別に君を求めてないけど 横にいると思い出す ♪君のドルチェ&ガッバーナの その香水のせいだよ このサビの部分でメロディーと歌詞が見事に合わされている
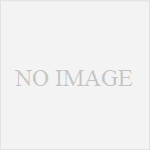
この歌詞、昭和の歌ですよねぇ。と言いながら、93年ってもう平成でした。そこで気になりましたので少し調べたところ、携帯電話が登場したのが1987年、1990年代半ばにポケベルが大ヒットしています。つまり、この歌がヒットした93年は、まだ携帯は普及はしてなかったことになります。そうなりますと、この歌の歌詞が意味を持ってきます。
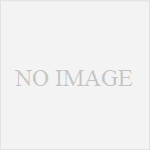
そういえば、昔はタバコを吸うのが当たり前だったんですよねぇ。「当たり前」というか、吸っている姿が「カッコよかった」と思い込んでいましたっけ。当時のドラマを見ると、主人公の方々はみなさん、必ずタバコを吸う姿をどこかに入れていました。なんか懐かしいです。
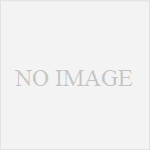
この言葉には痺れます。芸能界と聞きますと、まだ世の中を知らない少女をたぶらかし、言いくるめて利用して、儲けを搾取するというイメージが浮かびます。マスコミなどから流れてくる情報からしますと、全部とは言いませんが、そういうことが多そうです。
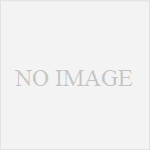
「このようなケースで『日本人の情報』を伝えると、必ずと言っていいほど「日本人のことだけを伝えるのは不公平」という意見が番組にきますが、私は「『日本人の情報』を真っ先に伝えるべきだと考えています」と話していました。
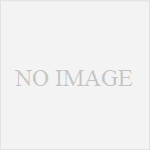
僕は山下さんのそれほどのファンではないのですが、70年代にヒットを飛ばした人たちの音楽史関連の本を読んでいますと、山下さんの名前は必ず出てきます。僕にはわからないですが、音楽性がダントツに高いらしいです。
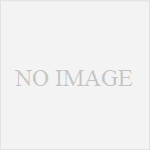
この歌の魅力はやはりなんと言ってもボーカルの中井昭さんの歌声です。ファルセットがかった歌声がなんともいえない昭和を醸し出しています。上記のとおりクールファイブと競っていたとは知りませんでした。しかも、クールファイブよりも先に世に出ていたにもかかわらず、一発で終わってしまったのは、レコード会社の力のなさではないでしょうか。
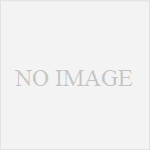
実は、なぜか、この歌は拓郎さんが作ってマイペースが歌っている、とずっと思っていました。しかも、僕が「好き」であるにもかかわらず、なんと100万枚も売れていました。驚き~。 それにしても東京を知ったばかりに恋が破綻する例は多いです。人って、環境が変わり年月が過ぎると性格も考え方も変わっちゃうから。難しいよなぁ。
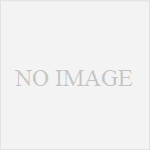
イントロはオーケストラではじまるのですが、自分が歌いだすまでの前奏で、オーケストラを見ている様が白髪とシワが刻まれた表情は観る人たちを引き付けてやみません。また、この前奏のときのカメラワークも絶品です。デンマークですので、北欧の美女の方々を随所に入れているのですが、その入れ方のタイミングも絶妙でした。そして、いよいよブルッカーさんが歌いだすのですが、そのしわがれた声質がまたなんとも言えず魅力的です。一気に宗教の世界へと引き入れます。
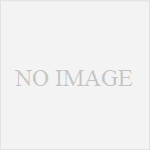
売野さんはチェッカーズでヒットを連発するのですが、その後はまったくジャンルの違う音楽の世界に転じています。これはクリエイティブな仕事に就いている人によくあるパターンですが、お金を稼ぐために「ヒット狙い」を続けたあと、人財産を築いたあとは本当に自分の好きな方向に進む人がいます。